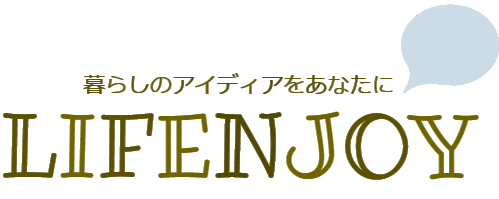お箸の歴史、種類
日本で最も多く使われている食器と言えばやはりお箸です。
日本の細い棒を使って食べ物をつまむという独特の動作で使用するお箸ですが、これが使われるようになったのはだいたい3世紀くらいのこととされています。
「日本書紀」や「古事記」の中には箸についての記録があり、この頃には一般的に使われていたということがわかります。
もう一つの箸の起源説として、7世紀に行われた遣隋使のときに小野妹子が中国から箸の文化を持ち込んだということもあります。
日本で箸という食器を一般的にしたと言われるのが聖徳太子で、朝廷の儀式においては箸を使うように定めたとされています。
8世紀くらいになると貴族だけでなく一般市民の間にも箸文化が広がったそうで、食事を手づかみではなく食器を使って食べるという文化的風習が誕生しました。
箸の優れた点は、食事をするための動作の多くを一つの食器で行えるということです。
食事をするときには、ものをつまんだり挟んだり、すくったりまとめたりといったいくつもの動作が必要になってきます。
上手に箸を使うことができるようになれば、箸で食べ物を切ったり魚の皮などをはがしたり、汁物を混ぜたりということもできますので、いちいち用途により食器を持ち替える手間が省けます。
全国には伝統工芸品として箸を制作している地域も多くありますが、箸にも形や塗装、使用される材質によりいくつかの種類に分類できます。
有名なものとして輪島塗など漆を縫ったものがありますが、塗装をすることによって箸を滑りにくくし耐久性を高めることが可能です。
箸には大きく「木箸」と「塗り箸」があり、素材の仕上げ方法によって分類されます。
調理時の活用方法
箸は個人で使用をする手元箸の他に、料理を取り分けるために使うものや、調理そのものをするときに使うものなどがあります。
調理用の箸には「真魚箸(まなばし)」と「菜箸(さいばし)」という二種類があります。
一般的に料理用として販売されているのが「菜箸」で、これは普通の木製の箸が大きなサイズになったもののことです。
もう一つの「真魚箸」は金属製をして先端が細く作られていることから、主に繊細な盛り付けが必要になる和食店などで使用されています。
菜箸は家庭で行う一般的な調理で行う炒めものや混ぜもの、魚の裏返しとったときに使用をします。
普通の箸で代用をすることもできますが、油を使った料理などは箸の長さがあることで安全に使用できるのです。
ちなみに本格的な和食店では、天ぷらを揚げる時専用の大きな箸や、蕎麦を茹でるときに使う竹製の太い箸なども使用をされています。
そうしたお店に行くときに箸に注目をしてみると、箸文化の奥深さを感じることができるでしょう。