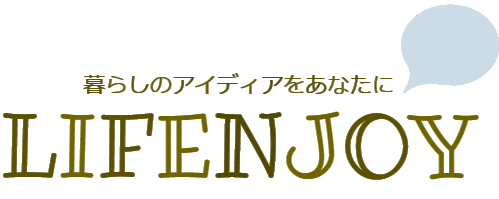香典とはそもそもどういうものか
葬儀への参列をするときに必ず持参をするのが「ご香典」です。
コンビニエンスストアや100均ショップに行けばさまざまな種類の香典袋を購入することができるので、参列をする前には必ずそうしたところで専用の袋を用意して必要事項を記載してから受付で渡すようにします。
「香典」とは葬式の参列者が自発的に遺族に渡す現金のことを全般的にそう呼ぶものですが、実はこれは比較的新しくできた習慣であり、過去には現金ではなくお香を持ち込んで渡していたということからその名称が引き継がれました。
これもかつては仏様に捧げるお香がとても高価なものであったため、葬式のときにそれを切らさないようにと参列をする人たちが寄付をするということから始まったものなので、基本的な主旨である「遺族に対する葬式にかかる費用への補助」ということではそれほどかけ離れたものではないといえます。
なお葬式においてお香を焚くという風習は仏教伝来のものであるため、神道による神式の葬儀やキリスト教の葬儀においては「香典」という言葉は使わずにそれぞれ「御玉串料」や「御花料」という名目に変わります。
最初に述べた香典袋にいくつかの種類があるのはそうした宗教によって呼び名が異なるてためで、購入時にはその葬儀がどういった方式で行われるかということを確かめてから間違の内容に用意をしましょう。
基本的な香典袋の書き方
最もメジャーな式方法である仏式の「ご香典」で書き方のマナーを説明します。
まず香典を渡すときには必ず専用の白地の和紙をたたんだところに黒白の水引きがかかった袋を使用します。
結婚式の場合には中に入れる金額によって袋のグレードを上げるという習慣がありますが、葬儀においてはかなり高額であってもごく普通の香典袋を使っていれば失礼にあたりません。
香典袋として購入をするときには最初から「御霊前」といった文字がついているものが便利です。
これは葬儀の方式によって香典の呼び名が異なるためで、「御霊前」という文字であればそれが神式でもキリスト教式でも問題なく使用をすることができます。
香典袋には水引きの下半分の中央に縦書きで自分の名前を書きます。
このときにはできるだけ筆で書くようにしましょう。
また市販の香典袋の場合には和紙の外包の中に封筒が入っているのでそこに現金を入れます。
封筒には「金○○万円」という入っている金額と裏面に自分の住所と氏名をわかりやすく書いておきます。
なお注意をしたいのが記載をするときの漢数字の書き方で、「一」は「壱」、「二」は「弐」といったふうに誤解のないようにきちんと書き込むようにしましょう。
参考>>香典袋の書き方
その他にも守っておきたいマナー
香典にいくらを包むのかということについてはなかなか議論が分かれるところです。
一応目安となるのは故人との関係と会葬者の年齢や社会的な地位です。
例えば現在30代の会社員が会社の同僚や同年代の友人が亡くなったという場合であれば、だいたい3千円~1万円くらいの金額でよいとされています。
ただ地域の習慣や宗教によってまた相場は異なるようなので、可能であれば自分の立場ならいくらくらいが適当かということをそれとなく周囲に確認しておくようにしましょう。
また香典として包むお金はいわゆる「ピン札」は使わないようにするというのも小さなマナーです。
急に参列をする場合でどうしてもピン札しかないというときには軽く折ってから包むようにしましょう。
香典返しを受け取るときのマナー
香典返しとは香典に対するご遺族からのお礼です。香典返しを受け取る側の言葉としては「ありがとうございます」というお礼の言葉は避けましょう。
それは、礼に礼を重ねることを連想させ不幸を重ねるという意味に転じることからです。「恐れ入ります」や「恐縮です」といった言葉に置き換えて挨拶するようにしましょう。
香典返しの種類って?
よく使われる香典返しの品物としては、お茶類や海苔などの乾物、お菓子や洗剤、タオルなどの日用品など定番でした。
しかし、最近の傾向としては少しでも荷物にならないようにとか、参列してくれた人の好みにあったお返しができるようにと、カタログギフトや商品券にする傾向があります。
どのような香典返しを選んで受け取ることになるかは、こちらをご参考にしてみてください。
参考>>香典返し法要のお返しのカタログギフト|カタログギフトのマイプレシャス
香典返しの種類にも「身内」、「会社関係」、「お手伝いしていただいた人」など、それぞれの参列者に適した多くのバリエーションもあるようです。
香典とは渡すときから香典返しをいただくまで、相手の気持ちを思いやるマナーのやりとりがあります。正しいマナーを身につけるようにしましょう。